お子さんの誕生を機に教育資金を考え始めたものの、「本当に学資保険で良いのだろうか」と立ち止まっていませんか?「学資保険は入らない方がいい」という意見の根拠と、ご家庭に合った賢い準備方法を、一緒に考えていきましょう。
【はじめに結論】学資保険と新NISAのどちらを選ぶか迷っている方のために、まず結論となるポイントを比較表にまとめました。保障を重視するか、資産の成長を重視するかで最適な選択は異なります。
| 項目 | 学資保険 | 新NISA |
|---|---|---|
| 目的 | 保障と計画的な貯蓄 | 資産形成(投資) |
| 安全性 | 元本確保型が多い | 元本保証はない |
| 収益性 | 低い(返戻率105%前後) | 高い期待値(年率3-7%等) |
| 柔軟性 | 低い(途中解約で元本割れ) | 高い(いつでも換金可能) |
この記事で分かること
- 学資保険に入らない方がいいと言われる7つの客観的な理由
- 学資保険とNISAのメリット・デメリットの徹底比較
- ご家庭の状況に合わせた教育資金の準備プラン
- 「入らない」という選択をした後に後悔しないためのポイント
合理的に考えればNISAが有利なケースが多い

先に結論からお伝えすると、コストパフォーマンスと効率性を重視するならば、新NISAを活用した資産形成が学資保険より有利になるケースがほとんどです。学資保険の最大の強みである「親の万が一の保障」も、実は割安な掛け捨て生命保険で代替できます。
ただし、ご家庭のリスク許容度や貯蓄への考え方によっては、学資保険が適している場合もあります。この記事を最後まで読めば、その判断がご自身でできるようになりますので、ご安心ください。
約6割の家庭が学資保険に入らない時代背景とは
ソニー生命の「子どもの教育資金に関する調査2024」によると、学資保険の加入率は38.4%となっており、今や約6割の家庭が学資保険以外の方法を選択しています。これは、かつての「教育資金=学資保険」という常識が、静かに変わりつつある証拠です。
この大きな変化の背景には、長引く超低金利政策による貯蓄性の低下と、2024年から大幅に拡充された新NISAのような、より効率的な資産形成制度が身近になったことが挙げられます。現代の合理的な考え方を持つ親世代にとって、学資保険は必ずしも最適な選択肢ではなくなっているのです。
「学資保険が当たり前」は昔の話?パパたちが抱える3つの本音
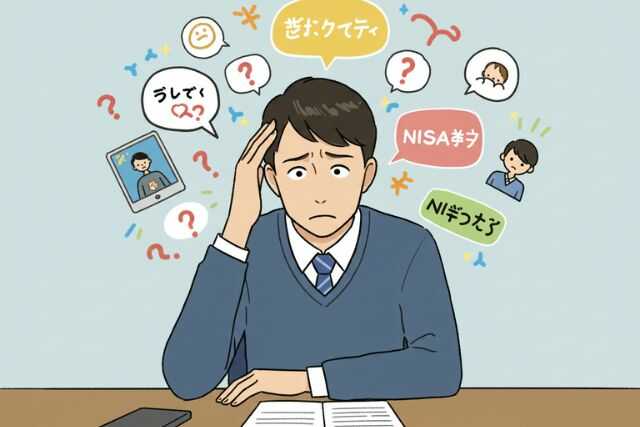
大切なお子さんの将来を想う気持ちは、いつの時代も変わりませんよね。けれど、そのための準備方法となると話は別かもしれません。特に、情報に敏感な30代のパパたちが抱える、学資保険に対するリアルな悩みや疑問を覗いてみましょう。
ALTテキスト: 若い夫婦が子供の将来の教育資金について計画している様子。学資保険に入らない方がいいか検討中。
周囲の意見とネット情報…結局どれが正解か分からない
親世代からは「子どものために学資保険に入るのが親の務め」と言われる一方で、友人からは「うちはNISAで準備してるよ」と聞かされる。さらにWebやYouTubeで調べれば「学資保険は時代遅れ」という辛口な意見も目にする…。
たくさんの情報に触れられるからこそ、「一体どれを信じれば良いのか」と判断軸が持てずに混乱してしまうのは、多くの方が経験することです。
低金利で増えないのに18年間も資金がロックされる不安
IT業界などで働く合理的な思考を持つ方ほど、学資保険の仕組みに疑問を感じやすいかもしれません。「18年間もの長期間、インフレにも負けるような低い利回りで資金を固定されるのは、明らかな機会損失ではないか?」という懸念です。
毎月コツコツ積み立てても、最終的に受け取れる金額が払込総額をわずかに上回るだけ。その間、もっと有効な運用ができたはず…と考えてしまうのは、ごく自然な感覚と言えるでしょう。
知恵袋の「いらない」「後悔した」の声で迷ってしまう
Yahoo!知恵袋などのQ&Aサイトで、実際に加入した方の「思ったより増えなくて後悔した」「途中解約で元本割れして損をした」といったリアルな声を目にすると、ますます不安になりますよね。
こうした第三者のネガティブな体験談は、パンフレットに書かれたメリットよりも強く心に響くもの。まるで、完璧な設計図と、実際に現場で起きたトラブル報告書を見比べているような感覚で、自分の選択が将来の「後悔」に繋がらないかと、慎重になってしまうのです。
学資保険をおすすめしない7つの理由と代わりになる賢い選択肢

「やっぱり入らない方がいいのかな…」その直感を裏付ける、具体的な理由を一つずつ見ていきましょう。なぜ多くの方が他の選択肢に目を向けているのか、その背景を理解することで、ご自身の判断にきっと自信が持てるはずです。
【経済的デメリット】貯蓄性が低くインフレで価値が目減りする
現在の超低金利下では、学資保険の返戻率(払った保険料総額に対する受取総額の割合)は高くても105%前後です。18年間で5%しか増えないというのは、年利に換算すると0.3%にも満たない計算になります。
さらに深刻なのがインフレリスクです。例えば文部科学省の調査でも示される通り、大学授業料は年々上昇傾向にあります。将来受け取る金額が固定されている学資保険は、教育費そのものがインフレで高騰した場合に対応できない可能性が高いのです。
【構造的デメリット】途中解約で元本割れ・資金が硬直化する
学資保険の大きな弱点は、資金の柔軟性(流動性)が極めて低いことです。家計が苦しくなるなどの理由で満期前に解約すると、解約返戻金が払込総額を下回る「元本割れ」を起こす可能性が非常に高くなります。
18年という長い期間には、予期せぬ出費が発生することもあります。そんな時にペナルティなしでお金を引き出せないのは、いざという時に身動きが取れなくなる、大きなデメリットです。
【保障のデメリット】医療特約で返戻率が低下・加入制限もある
「子どもの医療保障も付けられる」という点をメリットと感じる方もいますが、少し注意が必要です。こうした特約を付加すると、保険料の一部が保障に充てられるため、貯蓄性がさらに低下し、返戻率が100%を下回る(元本割れする)ことがほとんどです。
また、契約者(親)の万が一に備える「保険料払込免除」があるため、親の健康状態によっては加入を断られるケースもあります。保障と貯蓄は、それぞれ専門の金融商品で分けた方が、結果的に合理的になることが多いのです。
【機会損失】新NISAなど、より有利な資産形成の選択肢が登場
学資保険をおすすめしない最大の理由は、新NISAという、より強力な選択肢が登場したことにあります。NISAは投資で得た利益が非課税になる制度で、長期的に全世界の株式などに分散投資すれば、年率5%といったリターンも現実的に期待できます。
同じ金額を積み立てた場合、18年後には学資保険とNISAでは数百万円単位の差がつく可能性も十分にあります。この「機会損失」こそが、今、最も考慮すべきリスクなのかもしれません。
学資保険とNISAは結局どっちがいい?5つの視点で徹底比較

学資保険のデメリットは分かった。でも、NISAも投資である以上リスクがあるのでは…?その疑問、ごもっともです。ここでは、教育資金を準備する上で重要な5つの視点から、両者を公平に、そして分かりやすく比較します。
| 比較項目 | 学資保険 | 新NISA(全世界株式インデックスファンド等) |
|---|---|---|
| 収益性 | 低い(年利0.3%未満相当) | 高い期待値(過去実績では年平均5%等) |
| 安全性 | 満期まで続ければ元本確保 | 元本保証なし(価格変動リスクあり) |
| 保障機能 | あり(保険料払込免除) | なし(別途、生命保険で備える必要あり) |
| 流動性 | 低い(途中解約で元本割れ) | 高い(いつでもペナルティなしで売却可能) |
| 税金 | 受取時に課税の可能性あり | 運用益は完全非課税 |
収益性の違い:リターンはNISAが圧倒的に有利
すでにお伝えした通り、収益性ではNISAが圧倒的に有利です。複利の効果を活かして18年間という長期間運用することで、学資保険では到底得られないような資産の成長が期待できます。教育費のインフレにも十分対抗できるでしょう。
安全性の違い:「元本保証」の代わりに潜むリスクとは
学資保険の「満期まで持てば元本が保証される」という点は、確かに安心材料です。しかしその裏では、インフレによる「実質的な価値の目減り」という、見えにくいリスクを抱えています。
一方、NISAは投資であるため元本保証はありません。ところが、全世界の経済成長に連動するインデックスファンドなどに長期間・積立で投資することで、リスクは大きく低減できます。短期的な価格変動に一喜一憂せず、長期的な視点を持つことが大切です。
保障機能の違い:払込免除は学資保険だけの強み
契約者である親に万が一のことがあった場合、以降の保険料支払いが免除され、満額の学資金が保証される「保険料払込免除特約」は、学資保険にしかない最大の強みです。
NISAで準備する場合は、この保障機能がありません。では、どうすればいいのか。答えはシンプルで、万が一に備える部分は、割安な掛け捨ての収入保障保険や定期保険に別途加入し、必要保障額を確保しておくという合理的な対策が考えられます。
流動性の違い:急な出費に柔軟に対応できるのは?
資金の柔軟性では、NISAに軍配が上がります。NISAはいつでも必要な分だけペナルティなしで売却し、現金化することが可能です。急な病気や失業など、ライフプランの変更に柔軟に対応できるのは大きなメリットです。
税金の違い:非課税メリットと生命保険料控除を解説
NISA最大のメリットの一つが、投資で得た利益が全額非課税になる点です。通常、投資の利益には約20%の税金がかかるため、この恩恵は非常に大きいと言えます。
一方で学資保険は、支払った保険料が「生命保険料控除」の対象となり、年末調整で所得税・住民税が少しだけ還付されます。しかし、その節税効果はNISAの非課税メリットに比べると、残念ながら限定的です。
学資保険に入らない選択をする前のよくある質問と回答

ここまで読んで、ご自身の考えが整理されてきた方も多いのではないでしょうか。最後に、決断する前にもう一度確認しておきたい疑問点を、Q&A形式で解消していきましょう。
Q1. 入る場合のおすすめやランキング上位は?
もし、リスクを全く取りたくない、あるいは強制力がないと貯められないという理由で学資保険を選ぶのであれば、とにかく返戻率が高い商品を選ぶのが鉄則です。子どもの医療特約などは付けず、できるだけシンプルな貯蓄型に絞り込むという考え方もあります。ソニー生命や明治安田生命などが、常にランキング上位として挙げられます。
Q2. NISAで教育資金を準備する際の注意点
NISAで準備する際の注意点は主に3つあります。
- 長期・積立・分散を徹底する:短期的な値動きで売買せず、コツコツと積立を続ける。
- 低コストのインデックスファンドを選ぶ:全世界株式や米国株式(S&P500)などが定番です。
- 出口戦略を考えておく:教育費が必要になる数年前から、少しずつリスクの低い資産(現金や債券)に移すなどの対策を検討してみてはいかがでしょうか。
Q3. 親の持病で入れないケースはありますか?
はい、その可能性はあります。学資保険は生命保険の一種であり、特に「保険料払込免除特約」があるため、契約者である親の健康状態について告知義務があります。過去の病歴や現在の健康状態によっては、加入を断られたり、特別な条件が付いたりすることがあります。
Q4. 学資保険に入っている人の現在の割合は?
先に触れた通り、最新の調査では加入率は約4割です。これは、もはや学資保険が「入っていて当たり前」のものではなく、数ある選択肢の一つに過ぎないことを示しています。周りがどうしているかよりも、ご自身の家庭に合っているかどうかで判断することが大切です。
まとめ:学資保険に頼らない教育資金計画で未来に自信を

この記事では、学資保険に入らない方がいいと言われる理由から、代替案であるNISAとの比較まで、詳しく解説してきました。大切なのは、思考停止で「昔ながらの常識」に従うのではなく、現代に合った最適な方法を主体的に選ぶことです。
「入らない」という選択肢を肯定的に捉えよう
「学資保険に入らない」という決断は、決してネガティブなものではありません。むしろ、低金利やインフレといった現代の経済環境を正しく理解し、より合理的で効率的な方法を積極的に選ぶという、お子さんの未来を真剣に考えた上での前向きな選択です。
ご家庭のリスク許容度に合わせた最適な方法を見つける
最終的な正解は、一つではありません。例えば、こんな考え方ができます。
- リスクを取ってでも積極的に増やしたい → NISAで準備する
- 元本割れは絶対に避けたい。強制力も欲しい → 学資保険で準備する
- バランスを取りたい → 学資保険で最低限を確保し、NISAで上乗せを狙う
このように、ご自身の投資経験やリスクに対する考え方(リスク許容度)に合わせて、最適なポートフォリオを組むことが重要です。
最終的に迷ったら専門家への無料相談も有効な一手
もし、この記事を読んでもまだ迷いが残るなら、あるいはご家庭の状況に合わせた具体的なプランを知りたくなったら、一度専門家に相談してみるのも有効な一手です。無料相談などを活用し、中立な立場のファイナンシャルプランナーから客観的な視点でアドバイスをもらってみてはいかがでしょうか。
お子さんの大切な未来のため、自信を持って最適な一歩を踏み出しましょう。
